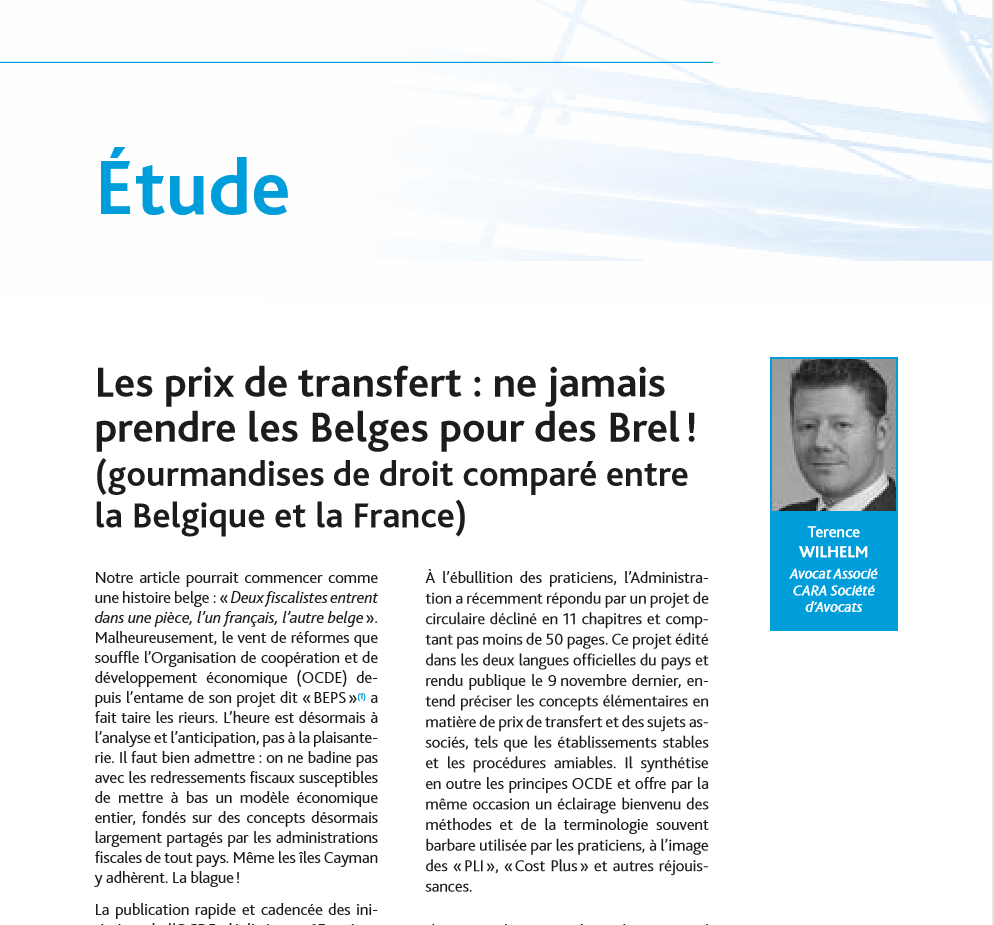この記事はベルギーの物語のように始めることができる。残念ながら、OECDがいわゆるBEPSプロジェクトを立ち上げて以来吹いている改革の風は、笑いを封じ込めた。今は、ジョークではなく、分析と期待の時なのだ。現実を直視しよう。ビジネスモデル全体を崩壊させかねないような税制調整を、現在では各国の税務当局が広く共有しているコンセプトに基づいて、ごちゃごちゃやっている場合ではないのだ。ケイマン諸島でさえも乗り気だ。何の冗談だ!
OECDのイニシアティブが15の具体的な行動に分類され、迅速に発表されたことは、まさに話題を呼んだと言わざるを得ない。現在では、誰もがそれぞれの意見や解釈を持っている。しかし、何十年にもわたって行われてきた国際課税に革命を起こさなければならないという点では、誰もが同意している。革命という言葉は正しい。フランスでは、この現象が決して円滑に進むことはなく、この問題における基本的な問題に対する無知が、矛盾した歴史の解釈を生むということを、私たちはよく知っている。
ベルギーの隣国は、この件に関してこれまであまり積極的ではなかったが、より賢明な行動をとった。実務家たちの熱狂に応えるように、ベルギー政府は最近、11章からなる50ページにも及ぶ通達草案を発表した。この草案は、移転価格に関する基本的な概念と、恒久的施設や相互協定手続きなどの関連事項を明確にすることを目的としている。また、OECDの原則を要約し、「PLI」、「コスト・プラス」など、実務家がしばしば用いる野蛮な手法や用語について歓迎すべき明確化を提供している。
このイニシアチブは歓迎すべきものである。政府部門が、移転価格の仕組みについて、自らの立場と解釈を明確に打ち出すべき時が来たのである。確かに、このサーキュラーは草案の段階に過ぎず、間違いなく多くの変更が加えられるだろう。仮に最終決定されたとしても、それは教義の価値しか持たず、基準の階層や法的確実性の追求という正当な目的の中では、限られた位置づけにとどまるだろう。確かに、このサーキュラーはベルギーの税務当局を拘束するだけであり、フランスの移転価格規制について直接的な結論を導くものではありません。この記事は、書きたいという欲求を満たすことを除けば、その範囲は限られているのです。
しかし、ベルギー税務当局が、フランスでいまだ議論の的となっている点、あるいは長期にわた る論争を煽っている点について、どのような立場をとっているのかは興味深い。ベルギー税務当局の最良の知見に基づく見解が、同じ問題についての我々の立場を修正し、あるいは強化することを促す可能性は高い。
「最高の取引は最も高い
このベルギーの古い格言は、まもなく廃れるだろう。サーキュラーの草案は、その第1章で、独立企業間原則を設定し、説明することから始まる。OECDの句読点のないシビレル式に対し、ベルギー行政当局は、ベルギーらしさであるシンプルさで逆襲し、次のように述べている。「この概念は、金融および商取引において、関連企業は、あたかも無関係であるかのように行動することが求められると規定している。関連企業が、非関連企業が合意しうる条件から逸脱する条件で合意した場合、移転価格は調整される可能性がある」2。
独立した取引の関連性を評価するための比較可能性の要素を示したが、法律の専門家にとって特に興味深い点がある。サーキュラー草案では、「移転価格の決定は、関連企業間で締結された企業間取引に関する既存の契約の分析に基づいて行われる。契約は、機能的分析が見出したものを表現することになっている。そうでない場合は、取引当事者の行動が優先され、契約条項は考慮されない」3。
そうすることで、ベルギーの行政は、契約を単なる推定に追いやるアングロサクソンの理論に味方しているように見える。ベルギーの法律は、わが国と同じ源流を持ち、何よりもまず書面法であることを忘れてはならない。契約は法体系全体において重要な役割を担っており、租税法に特有の性質があることは明白である。
確かに、フランス法では、税務判事は長い間、取引の公正価値を回復するために当事者の意向を再確認する権利を行政当局に与えてきた4。しかし、再確認は立ち退きとは異なるため、税務当局は法律行為の存在を考慮しなければならない。ベルギーの対応にあるように、契約を無視するためには、行政はやはり権利の濫用に関する特別な手続きを実施しなければならない。再確認と立ち退きの間のこの境界線は、形式よりも実質を、契約の外観よりも当事者の実際の行動を優先させるために、回章草案では軽々しく越えているように思われる。書面法というフランスの立場は、この先も長く続くのだろうか。
移転価格の計算における補助金と税額控除の扱い
私たちが注目したもう一つの要素は、この章の一番最後にある「その他」のセクションに控えめに隠されている。この章では、「補助金」の取り扱いと、報酬の算定に含まれる「補助金」の独立企業間価格を検証する必要があります。これらの「補助金」には、助成金と税額控除または減額が含まれる。このテーマは、ヴェルサイユ控訴院5で下され、コンセイユ・デタ6で支持された「フィリップス」判決による混乱を彷彿とさせるため、フランスの実務家の好奇心を刺激することは間違いない。
この場合、フィリップス・フランスは、フランス国から企業競争力強化基金による補助金と研究税額控除による金額を受ける研究活動を行った。フィリップス・フランスは親会社と一般サービス契約を締結し、前述の研究活動から生じた特許性のない無形権利の所有権を、対応する事業の原価に10%を加算した価格で親会社に譲渡することを約束した。監査において、フランス税務当局は、フィリップス・フランスが契約の適用にあたり、親会社に譲渡した無形資産の取得原価を決定する際に、フランス国から受領した補助金および研究税額控除を控除し、その後に10%のマークアップを適用して親会社への請求価格を決定していることを指摘した。税務当局は、この控除がフランス一般税法第57条の意味における海外への間接的な利益移転につながると考え、同社の所得を、販売価格を決定するために使用した原価に、これらの補助金および税額控除額を加算した金額だけ増加させた。
そこで問題となったのは、フランスで適用されている優遇制度で受け取った金額を、マージンを計算するベースから差し引くことが妥当かどうかであった。そうすることで、コストベースが大幅に削減され、10%のマージンがほんのわずかとなる。同社が提出した主な論拠は(巧みな弁護であったことは認めざるを得ないが)、優遇措置は、その適用範囲に含まれる納税者の投資と研究努力の見返りであり、従って、これらの制度から切り離された移転価格の主題を汚すものではないというものであった。一方の対象から他方の対象への影響を引き出すためには、やはり独立した第三者が、その価格設定において得られた優遇措置の効果を転嫁していることを証明する必要があった。この主張は正鵠を射ており、最後の租税判事は行政側の試みを打ち切った。
もし行政側の弁明が異なるもので、永遠の立証責任から切り離されたものであったなら、この問題はより良い結果に値しただろう。いずれにせよ、ベルギーの行政は、「補助金と製品の生産/回転またはサービスの提供との間に直接的な関連性がある場合、補助金は原価/回転ベースから控除される。補助金と製品の生産/回転またはサービスの提供との間に直接的な関連性がない場合、補助金は原価ベースから控除されない。税控除は、コストベースから控除されない。例えば、投資手当は原価から控除されない」7.
そうすることで、ベルギー税務当局は、フランスの税務判事と対立する、明確かつ明白な姿勢を採用した。従って、もしこの事件がジャック・ブレルの国で判決されていたら、この税務署は自分たちに有利な判決を下していただろうと考えることができる。
フランスとベルギーは移転価格算定方法について同じ見解を持っている
サーキュラー草案の第2章は、移転価格算定方法に充てられている。この文書では、それぞれの方法について明確な説明がなされている。DVNIが8日目に作成した手引きは、発行から10年以上経った今日でも、その図解で素人を啓発している。
ベルギーの行政当局は、コスト・プラス価格決定法に関する説明の中で、報酬の対象となるコスト・ベース、より具体的にはこのベースに計上される変動について見解を示している。実際、企業経営においては、当初の予測と実際の業績が大きく変動することはよくあることである。この点に関して、通達草案は2つの側面に光を当てている。
第一に、この文書では、実務上、移転価格は一般的に予算化されたコストに基づいて事前に決定されることを指摘している。そのためベルギー政府は、予算原価の使用による取引への影響、実際の原価との差異、選択された原価の種類(予算原価か実際の原価か)の長期的な持続可能性を監視すると述べている。また、「取引に関連する実際の費用が予算原価よりも体系的に高い場合、または予算原価の使用によって独立企業間原価と一致させることができない場合には、調整が可能である」と明記している9。
この意味論は重要であり、査察官に監査を実施する際の柔軟性を促すものである。経理部門から提供される実際のデータに基づいて移転価格を体系的に調整するよう求めることは、企業側に新たな労力を要求するだけでなく、何よりも調整すべき内容や時期が問題となる。毎年、会計年度末になると、会計士、監査人、財務担当者の小宇宙が、この調整をどのように処理するか、会計年度の決算を修正するか、翌年度のクレジット・ノートや追加インボイスを入力するかで大騒ぎになる(これらのジェスチャーに関連するVATや在庫価格の問題を提起することなく!)。したがって、ベルギー税務当局が現在とっている見解は、この問題が組織的でなく限界的なものである限り、この問題を無視することを認めています。
第二に、そしてより重要なこととして、この通達は、コスト・ベースにおいて観察されるスリップについて興味深い見解を示している。非効率によるコストアップは、商品やサービスを供給する企業が負担するのが一般的である。このような状況では、独立した買い手はいかなる価格調整も受け入れることはない。
バリューチェーンの各プレーヤーに説明責任を負わせることで、この文書は、行政(特にフランス)に見られる、被検査企業が日常的なプロフィールを担うやいなや、損失のリスクから保護され、これらのコストに対して組織的にマージンを生み出すべきだと考える傾向に深刻な打撃を与える。あたかも、現実の経済の世界では、独立したプレーヤーは、サプライヤーがコストを垂れ流し、恥知らずにもそれを請求することを受け入れるかのように。
この常識的な姿勢は、残念ながらあまり知られていないが、ベルサイユ控訴裁判所で下された原則的な判決を想起させる。この判決は、ユニリーバ・グループから請求された調整に続いて下されたものであり10、非効率のコストは、その原因となっていない当事者に負担させるべきではないことを立証することによって、同じ結果を招いた。
このケースでは、後にユニリーバ・フランスとなるアストラ・カルヴェ社が、フランス全土の4つの工場でマーガリンを製造していた。販売はグループ内のベルギー企業(驚くべき偶然の一致)に、価格プラス10%方式で行われた。このマージンは、他の同様の工場で観察される通常の生産率に基づいて計算された生産投資資本に適用された。しかし、このマーガリン工場は、特に設備の一部が陳腐化していたことに起因する深刻な効率性の問題を抱えていた。実際、これらの要因は、生産コストが予測を大幅に上回っていたことを意味し、一見余裕のある10%のマージンでは営業損失を相殺することができなかった。税務当局は、交渉で決められたマージンを確保したいと考え、工場の非効率性に関連するものも含め、発生したすべてのコストをコストベースに含めることが適切であると考えた。税務判事は異なる見解を示し、同局の主張を退け、工場を適切な管理責任に戻した。
このような知的アプローチは、合理的ではあるが、各経済プレーヤーは、そのリスクをコントロールするために物質的、人的、財政的資源を集中させることを前提に、自らが被るリスクの結果を負担しなければならないということを思い起こさせるOECDの最近の活動を待たなければならなかった。この点で、ベルギーの通達草案は、この概念を具体化したものであり、行政が今後遵守しなければならない常識的な原則を定めたものである。これが国境を越えて実現することを期待しよう!
注目される比較分析
サーキュラー草案の第3章では、移転価格の独立企業間価格を証明する際の核となる比較可能性分析に焦点が当てられています。比較可能性分析は、関連取引が独立企業間原則を遵守しているか、ひいては市場条件を遵守しているかを評価するために使用されるすべての移転価格算定方法にとって重要である。比較可能性分析は、使用される移転価格を正当化するための基礎となる」11。
移転価格問題における立証の弁証法の要として、比較可能性の探索を位置づけることを目的とするこの傾向について、少し考えてみよう。フランス側では、このアプローチは、税務当局と法律専門家の一部との相互肥沃化の結果であるように思われる。この法律専門家は、経済分野に目を向けるあまり、異常性の立証が何よりもまず法律問題であり、租税法の特殊性を消し去ることはできないことを忘れてしまっている。率直に言えば、移転価格は法律問題である。確かに、移転価格は経済学や金融学から借用した概念に基づいている。しかし、私たちの法律、特に民法の最も基本的な概念を避けて通ることはできません。
この前提を念頭に置いて、一般税法第57条第4項と最終項は、「規定された調整を行うための正確な情報がない場合」に限り、通常営業している類似事業との比較によって課税所得を決定すると規定している。言い換えれば、比較可能性分析は税務当局にとって代替的な手法に過ぎず、税務当局はまず、どのような手段であれ調整を行うよう求められているのである。例えば、同じグループ内の2つの会社間で、比較可能な会社の水準を上回る報酬を定めた契約があったとします。当事者間の著しい不均衡が証明されない限り(ちなみに、これも契約法から借用した法的概念です!)、契約は税務当局に対して執行可能であり、したがって税務当局は、経済分析とは無関係に契約の履行を要求できるはずです。また、比較可能性に関する調査のこの補完性は、非常に慎重な方法ではあるが、かつてのLivre des procédures fiscalesのL13AA条にも反映されており、このような調査は「方法が要求する場合のみ」(言い換えれば、移転価格を決定するために使用される方法)作成する必要があった。
今日、比較可能性の調査は準自動的なものであり、税務判事は、現在広く使用されている同判決を何度も繰り返し引用している:「フランスで設立された会社が、その関連会社である外国会社に対して請求した価格が、通常、すなわち独立企業間において営業している類似の会社が請求した価格よりも低いと認められる場合、税務当局は、フランス会社にとって少なくとも同等の対応関係があったことを証明することができない限り、フランス会社の業績に再統合する権利がある優位性の存在を立証したとみなさなければならない。しかし、そのような比較対象がない場合、税務当局は、このようにして確立された利益移転の推定を発動する権利はなく、企業が不十分な価格で役務を請求することによって自由を与えたことを証明するためには、合意された価格と移転された財産または提供された役務の市場価値との間に不当な差額が存在することを立証しなければならない12。
当局がこれに追随するのに必要だったのはそれだけだった。新バージョンの文書化義務に関する最近の教示の中で、フランス税務当局は恥ずかしげもなく、比較可能性分析の作成が不可欠であることを明言している。その中で、「会社とその関連会社の詳細な比較可能性分析と機能分析は、各取引カテゴリーについて、前年からの変更点を反映させて作成されるべきである」と明確に述べている。各取引カテゴリーについて、比較可能性分析は、会社の報酬条件を記述し、独立企業の報酬条件との差異を正当化する」13。
もちろん、独立企業間という原則は、企業が第三者と同じように行動することを求めている。したがって、比較可能性分析があらゆる移転価格調査の中心にあると考えるのは短絡的である。しかし、すべてを比較したいという願望は、外生的であれ内生的であれ、価値のベクトルとして作用する特異性や要因を曖昧にしてしまう。ナルキッソスが破滅を迎えたように、自己の反映を求めることは必ずしも美徳ではない。
比較可能性分析の盲腸
このような考慮はさておき、このサーキュラー案は、ベルギーの観点から、信頼できる比較対象品探索の概要を示している。このアプローチは、誤った解釈や技術者間の紛争を制限することにより、法的確実性を追求するという目的を達成するものであると考えれば、称賛に値するものである。しかし、それぞれの状況に特有の特徴に対処しておらず、別のアプローチが必要となる可能性がある。とりわけ、ベルギーのモデルを主張することによって、他の基準に基づくことができる外国で実施された研究(特に、試験を受けた当事者がベルギーの領域外に所在する場合)を事実上排除することにつながる。
例えば、サーキュラー草案では、OECDの複数年データの使用に関する勧告が追加されている。同ガイドラインは、「複数年データの検討は比較可能性分析において有用であることが多いが、体系的な要件ではない。移転価格分析が改善される場合には、複数年データを使用すべきである。複数年分析でカバーしなければならない年数について基準を設ける必要はない」14。しかし、ベルギー政府はさらに踏み込んで、「比較対象企業の分析においては、少なくとも3年間を考慮すべきである」と考えています15。実務上、これはフランスの行政当局が一般的に適用しているアプローチとも一致しており、フランスでは監査対象年度の前年度より前の3年間を使用することが好まれる傾向にある。
しかし、よくあることだが、悪魔は細部に宿り、本質的なポイントは文章の後半部分に隠されている。プロジェクトはこう続ける。「一方、テストされる部分については、データは論理的に、ある年に調査された取引に関するものに限定される」。
この主張は、フランスの行政の常套手段であることは認めざるを得ないとしても、私たちには意外に思える。実際、このような恣意的な手法と、行使の独立性の原則や、(例外を除いて両国とも3年間という)回復の権利をどのように一致させることができるのだろうか。このアプローチでは、特定の年に観測される可能性のある外生的な経済効果を捉えることはできない。
フランス当局がこのような措置を取るとすれば、2009年のヴェルサイユ行政裁判所の決定がそれを妨げる可能性があると我々は考えている。Man camions et bus」事件において、税務判事は、フランス市場におけるルノーのような経済的プレーヤーの存在の優位性を無視し、汎欧州的な言及に集中することによって、行政当局に課せられた弁証法的証明に失敗したと裁定し、大臣の主張を退けた16。ひいては、特定の年に市場に影響を与えた経済的要因を十分に捉えていないことで、比較可能性分析には必然的に欠陥があると考えられる。
もうひとつの注目点は、比較対象として選んだ参考文献の出所である。ベルギーの行政はフランスの行政よりも勇気があり、明確な立場をとっている。そのため、いわゆる「外部」の比較対象を探す場合、「行政は汎欧州的な研究を受け入れ、できれば2014年の拡大以前にEUに加盟していた15カ国をベースとすることが望ましい」と通達案では述べられている17。
共同体法に照らせば、税務当局が必然的に国内の比較対象を使用するよう要求することで、国内優先主義を示すことはできないのは明らかである。ベルギーの行政当局がブリュッセルの裁判官たちから制裁を受けるのは、言語道断である!しかし、加盟国間の市場の違いが大きいことを考えれば、27カ国の欧州の比較対象を使用することは、我々にも関係がないように思われる。私たちとしては、前述の「マン」判決で強調されたような各セクター特有の特徴を考慮することを条件として、この立場を支持する。
敗戦のハロ
同章で税務当局は、「その間の比較対象について、税務当局は2年以上の赤字決算のある会社を認めない」と露骨に述べている18。この前提は、明らかに両国の監査人が広く共有している傾向と一致しているが、最も基本的な経済・税務の概念に反しているように思われる。
景気循環の気まぐれは、残念ながら慢性的な赤字につながる可能性があることを忘れてはならない。ベルギーやフランスのように、長い間赤字を垂れ流しているような国についてはどうだろうか。このような環境下で、政府がとっくの昔に見切りをつけたような財政スタンスを経済プレーヤーに求めるのは馬鹿げているように思える。
さらに、特定の経済分野や市場戦略では、将来より好収益を生むことを期待して大規模な投資を行う必要がある。これこそが起業家精神の本質である。従って、赤字企業の排除を提案することは、監査対象となる納税者とは潜在的に異なる経済的・商業的サイクルにあるプレーヤーのみを捕捉する危険性がある。そうすることで、このアプローチは、比較可能性分析の基本的な要素、すなわち OECD の 5 つの基本基準の一つとして挙げられている企業戦略を無視することになる19。さらに言えば、このアプローチは、必然的に徳が高く、市場の気まぐれから守られている企業について、滑らかで不正確、したがって歪んだ反映を納税者に送ることになる。このような優遇措置が現実には何の根拠もないことは言うまでもない。
法的な観点からは、正法のどこにも2年以上の損失計上を禁止する記述はないことを忘れてはならない。それどころか、繰越控除の仕組みは、納税者が損失を出す可能性を暗黙のうちに、しかし必然的に認めている。したがって、税法が認めている移転価格税制を否定することは困難である。
とりわけ、赤字企業を比較対象から除外することは、実際には、独立した第三者企業に提供される自由を被監査納税者から奪うことを意味する。そうすることで、独立企業間競争の原則は、この状況がもたらす明らかな待遇の違いによって崩れ去ることになる。
この不正の匂いは、グループの一員であることから生じるいわゆる「暗黙の」保証をめぐり、第三者企業が知ることのできない、単に暗黙の取引に対する報酬につながった、以前の根拠のある議論を思い起こさせるだろう。フランスの裁判所は、ボルドー行政裁判所の原則判決20でこの議論に終止符を打ち、その直後にコンセイユ・デタ21がこの判決を取り上げた。ハロー効果」を扱ったこれらの判決において、解決策は明白であった。
最後に、フランスでは現在、営業損失はそれ自体では移転価格目的の間接的な利益移転を証明するのに十分ではないという趣旨の判例が確立していることを指摘しておく22。
今回ばかりは、法律と経済学が同じ波長を持ち、2年間損失を出した比較可能な企業を除外するというベルギー行政のアプローチを、全面的に否定するわけではないにせよ、強力に緩和することを支持している。フランス側としては、たとえ監査法人が同一のアプローチを採用したとしても、納税者はそれに対抗するために必要な武器を持っていると考える。
今日論争の的になっている問題の解説歓迎
歓迎すべき取り組みである。このサーキュラー草案は、OECDの最も現代的で監査可能な分野、すなわちグループ内サービス、無形資産、関連企業間の財務関係についての最近の動向を説明することを目的としている。この3つのトピックだけで報告書のほぼ半分を占めている。
現場での観察から得られた非公式な統計によると、この種の取引は定期的に監査部門の注意を引くため、当然ながら通知される調整の大部分を占める。よく言われることだが、対象はさほど複雑ではないものの、移転価格に関しては、監査部門が最も得意とするところである。子会社に再請求するベースから株主の費用を控除しなかったり、債務者である子会社に提供された便益を詳細に説明しなかったりするグループがどれほどあるだろうか。
この点に関して、サーキュラー案は、いわゆる「低付加価値」サービスの処理方法を定めており、これにより、これらのフローに関係する納税者の書類作成や裏付け書類の負担が大幅に軽減されるはずである。
政府が無形資産やキャッシュフローを含む取引に注目しているのは、むしろ現代を反映している。前者は現代経済の本質を反映したものであり、重要な成功要因は今やほとんど無形要素にしか具現化されていないという事実を示している。後者は、2008年の危機を契機に始まった政治的な動きの延長線上にあるもので、金融と、企業グループのような統合された機関の中で知的に考え抜かれた資本移動から生じうる濫用に非難の矛先を向けたものである。
無形資産に関する限り、ベルギーはここでもまた、自国の成文法文化から距離を置き、OECDの新原則に影響を与えるアングロサクソンのテーゼを採用している。特に無形資産の分類に関して、政府は次のように発表している。「無形資産に適用される会計基準に準拠しないことを明確に選択した。したがって、無形資産は、その使用または処分に対する報酬を請求できるようにするために、企業の年次会計に常に表示される必要はない。 また、無形資産は、その使用や処分に対する報酬を請求するために、法律で保護されている必要もない23。そうすることで、ベルギーの行政は、無形「要素」という概念に向かいつつある。この概念は、もはや自発的に権利と呼応するものではなく、その輪郭はより確実であり、資格も想定されている。本論文は、アメリカの理論家によって開発された有名な「価値あるもの」に言及している。この概念は、会計上あるいは法律上の定義から逃れ、価値をもたらす無形の要素という考え方を反映したものである。ある意味で、この概念は、評価者にはすでに知られている「のれん」に相当する。
当分の間、この措置はフランスの税務当局によってとられることはなく、税務裁判所によってもとられることはない。わが国の法体系には、文書化された法律への愛着が浸透しており、適切な税務処理を適用するためには、その流れを明確にする必要がある。
同じように、ベルギーの行政は、無形資産の法的所有権から、「DEMPE」24として知られる本質的な機能の遂行と管理に反映される経済的所有権に重点を置きつつある。そのため、契約書や権利証は単なる手がかりに過ぎず、運用上の現実は無視されることになりかねない。ここでもまた、同じ制度がフランスで再現された場合、権利の濫用という極めて限定的な場合にのみ契約を完全に無視することを認める財政法(Livre des procédures fiscales)第L64条にどのように適合するかは疑問である。
もう一つの重要な進展は、ベルギー税務当局がOECDの「事後」アプローチを支持したことである。このアプローチは、無形資産が取引の対象となり、その評価の基礎となる状況がその後大幅に変化した場合に、税務当局が無形資産の価値を再評価することを認めるものである。ここでもまた、このアプローチは、契約の無形性と強制力という文書法の著名な概念に反している。わが国の民法では、契約は物と価格について合意があったときに成立し、不変のものとなる。もちろん、その原因や目的について明らかな誤りがあったことや、当事者の義務に不均衡があったことが後に証明されない限り、である。
とりわけ、この事後的アプローチは、税務当局が回収期間を延長することを可能にする。関連する二重課税協定を誠実に履行する一環として、税務当局は、無形資産が処分された会計期間の終了後7年以内に、上記の原則に従って移転価格を調整する」25。
フランスでは、税務判事は、市場の発展によりブランドの価値が変化したことを理由に、取引から数年後に当局が価格を再評価することはできないと裁定している26 。経済の本質はランダムであるということであり、納税者がその変動を予測することは非常に容易であろう!水晶玉がなければ、納税者は事業の成否を常に予測することはできない。新しい特許や競合ブランドのリリースは、これらの要素の価値を損なう可能性があるため、売却価格や譲受価格に反映される本質的な価値を損なう可能性がある。OECD の動向を鑑みると時代遅れに見えるかもしれないこのアプローチは、下取り期間を通常法 の期間に限定し、契約の拘束力を保護することにより、より高度な法的確実性を保証するものである と我々は考える。
最後に、金融取引に関して、このサーキュラー案は、そのような取引に関わるケースを処理する際に行政が考慮する要素をいくつか提示している。第X章は、グループ内融資、融資に対するグループ内保証の提供、自己契約について順次取り扱っている。これらすべてのフローを分析する際に中心となる「格付け」(または信用格付け)の概念も、最初のセクションに明記されている。この点に関して、ベルギー税務当局は、フランスの税務判事がすでに扱ったことのある「ハロー」概念を事実上排除することで、OECDの立場と足並みを揃えた。草案では、「また、暗黙の保証に対していかなる補償も支払われるべきでないことも念頭に置く べきである」27。
本章では、ベルギーの行政当局がOECDの原則を採用し、金融フローの独立企業間取引(arm's length nature of a financial flow)を判断する際に、逐次的なアプローチを奨励していることを示している。この文脈では、専門的なデータベースへのアクセスは必要以上であろう。しかし、このような取引には主観が入り込む余地がほとんどないため、同様の効果により分析が容易になるはずである。
結論として
ベルギー税務当局のアプローチは歓迎すべきものです。多くの重要な概念を明確にしているだけでなく、多くの問題について税務当局の意図を明確に示しているというメリットもある。わがフランスの行政当局も、内容が必ずしも明確でない行政指導を長年にわたって垂れ流すのではなく、この方式を模倣することをお勧めする。しかし、OECDの仕事に対する明確かつ顕著な愛着を通じて、この通達はベルギー税法の新たな側面を提示しており、現在では明文化された法律よりも経済合理性により傾いている。この文書はまだ草案の段階である。調整が加えられることは間違いないが、この野心的な最初の草案は、すでにベルギーとフランスの両政府の今後の管理分野を浮き彫りにしている。ブレルは "quand on a que l'Amour "と歌った。それはBEPSのずっと前のことだ。そして今、移転価格税制は明らかにその流れに乗りつつある!
2/ Circulaire relative aux prix de transfert, p. 5. 3/ 同上 4.
/ 5/ CAA Versailles, 11 Oct. 2016, n° 14VE02651. 6/ CE, 8ème et 3ème ch. réunies, 19 Sept. 2018, n° 405779. 7/ Circulaire relative aux prix de transfer, p. 7 and 8.
8/ 移籍金、PME使用ガイド、2006年11月 9/ 移籍金に関する通達、12頁 10/ CAA Versailles, 6ème ch. 5 déc. 2011, n°10VE02491。
CE, 8ème et 3ème ch. réunies, 19 Sept. 2018, n° 405779. 13/ BOI-BIC-BASE-80-10-40-20180718, published on 18 Jul. 2018, BIC - Tax base - Indirect transfer of profits between dependent enterprises - Documentary obligation allowing transfer pricing to be controlled, §430. 14/ OECD 移転価格ガイドライン(多国籍企業と税務当局のための), July 2017, §3.
15/ 移転価格に関する通達、18 ページ、§83. 16/ 移転価格に関する通達、CAA Versailles, 3rd ch. 2009 年 5 月 5 日、n°08VE02411. 17/ 移転価格に関する通達、21 ページ、§108. 19/ 移転価格に関する通達、21 ページ、§111.
20/ CAA de Bordeaux, 3ème ch. 2 sept. 2014, n° 12BX01182. 21/ CE 9eme et 10ème ch. réunies, 19 juin 2017, n° 392543. 22/ 最近の例としては、TA Melun, 3ème ch. 14 juin 2018, n° 1502063.
23/ Circulaire relative aux prx de transfert, p. 21, §137. 24/ OECDは、開発(Development)、強化(Enhancement)、維持(Maintenance)、保護(Protection)、運用(Operation)の頭文字をとっている25。
26/ 移転価格に関する通達、21頁、§168。 27/ 移転価格に関する通達、21頁、§264。